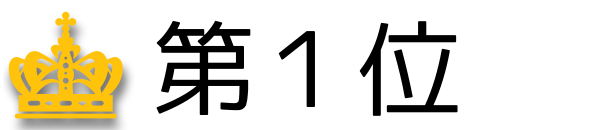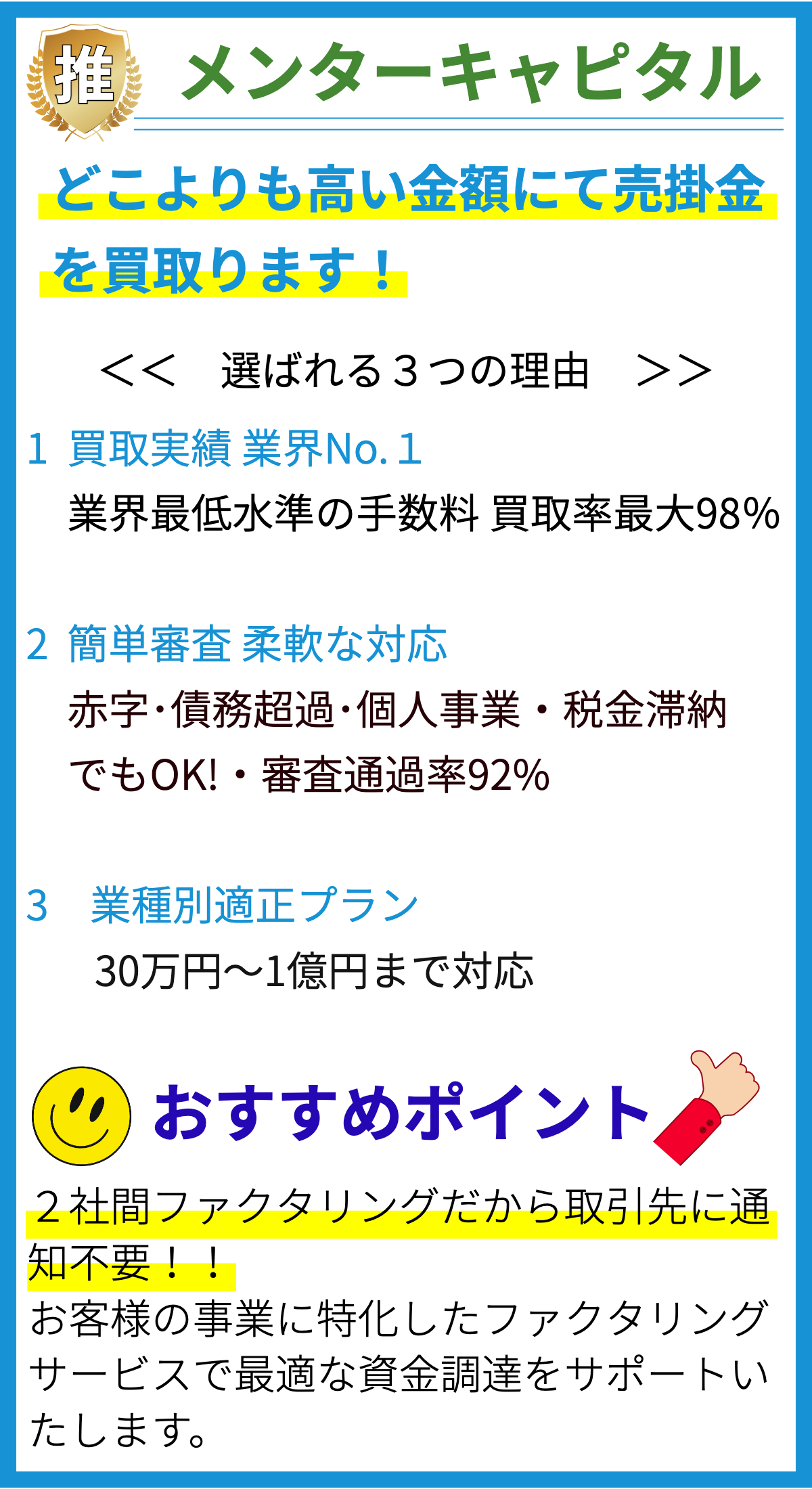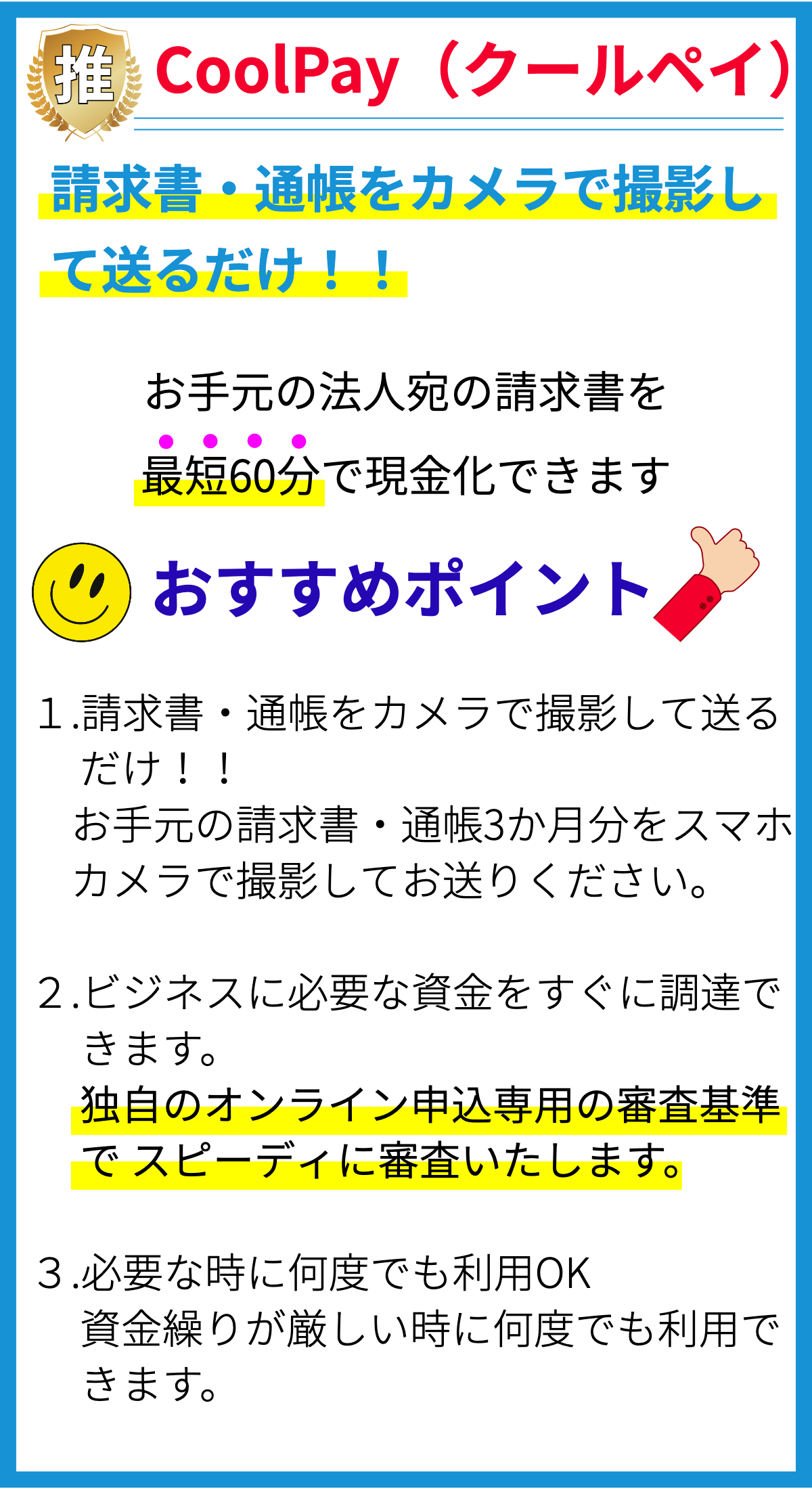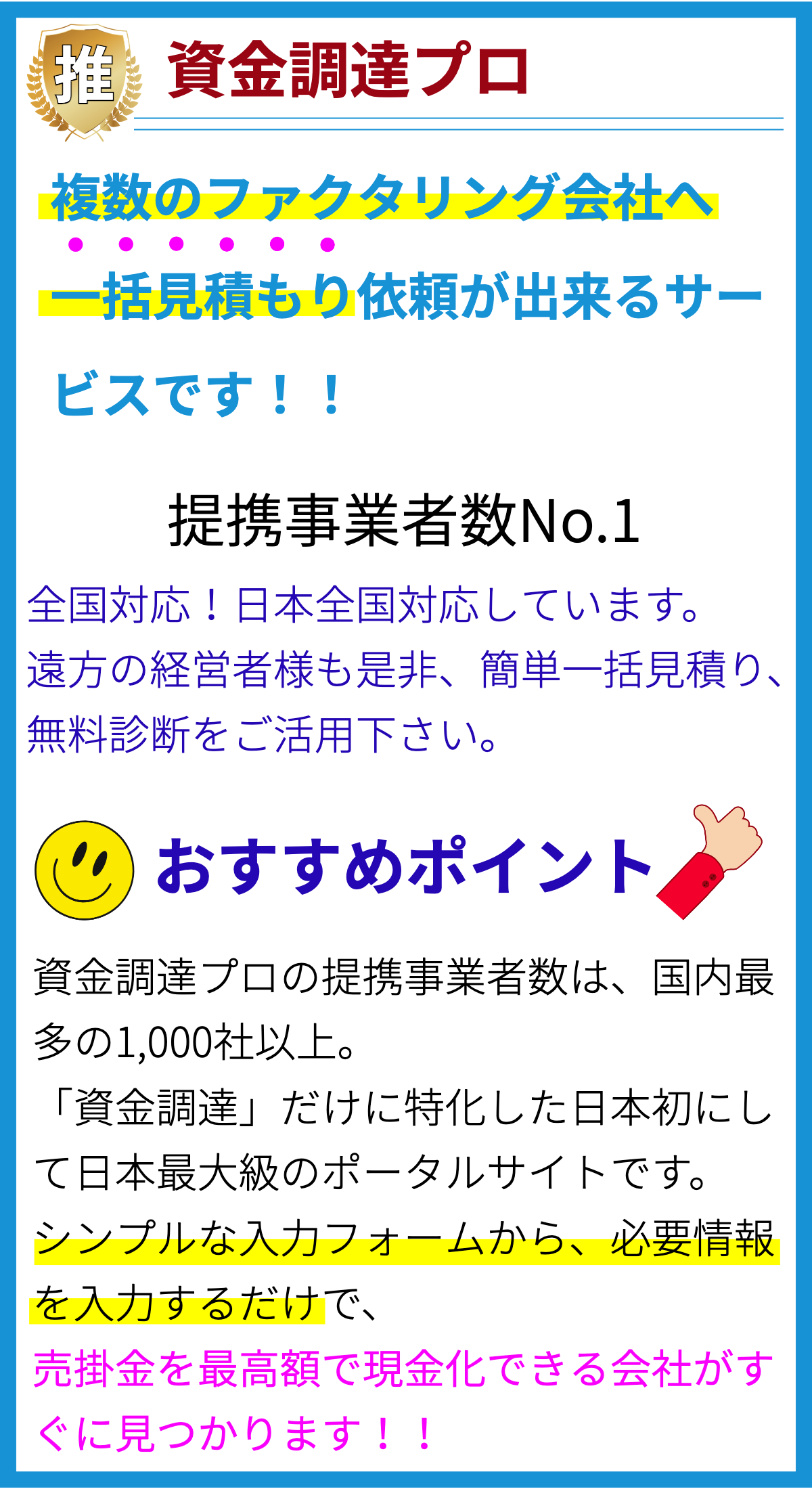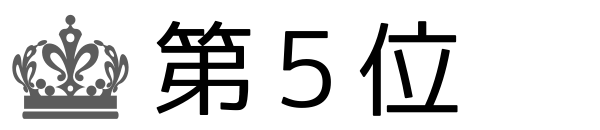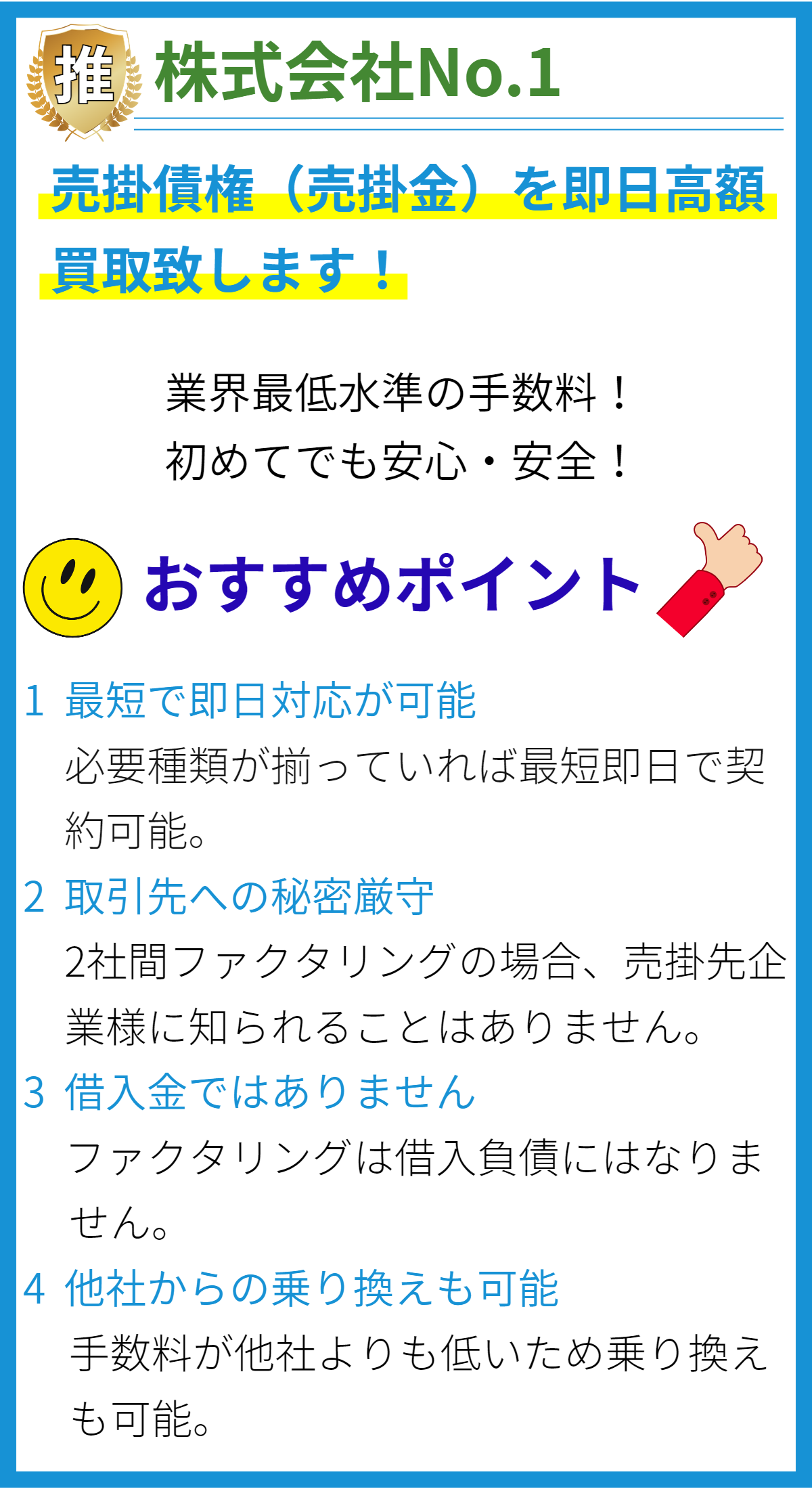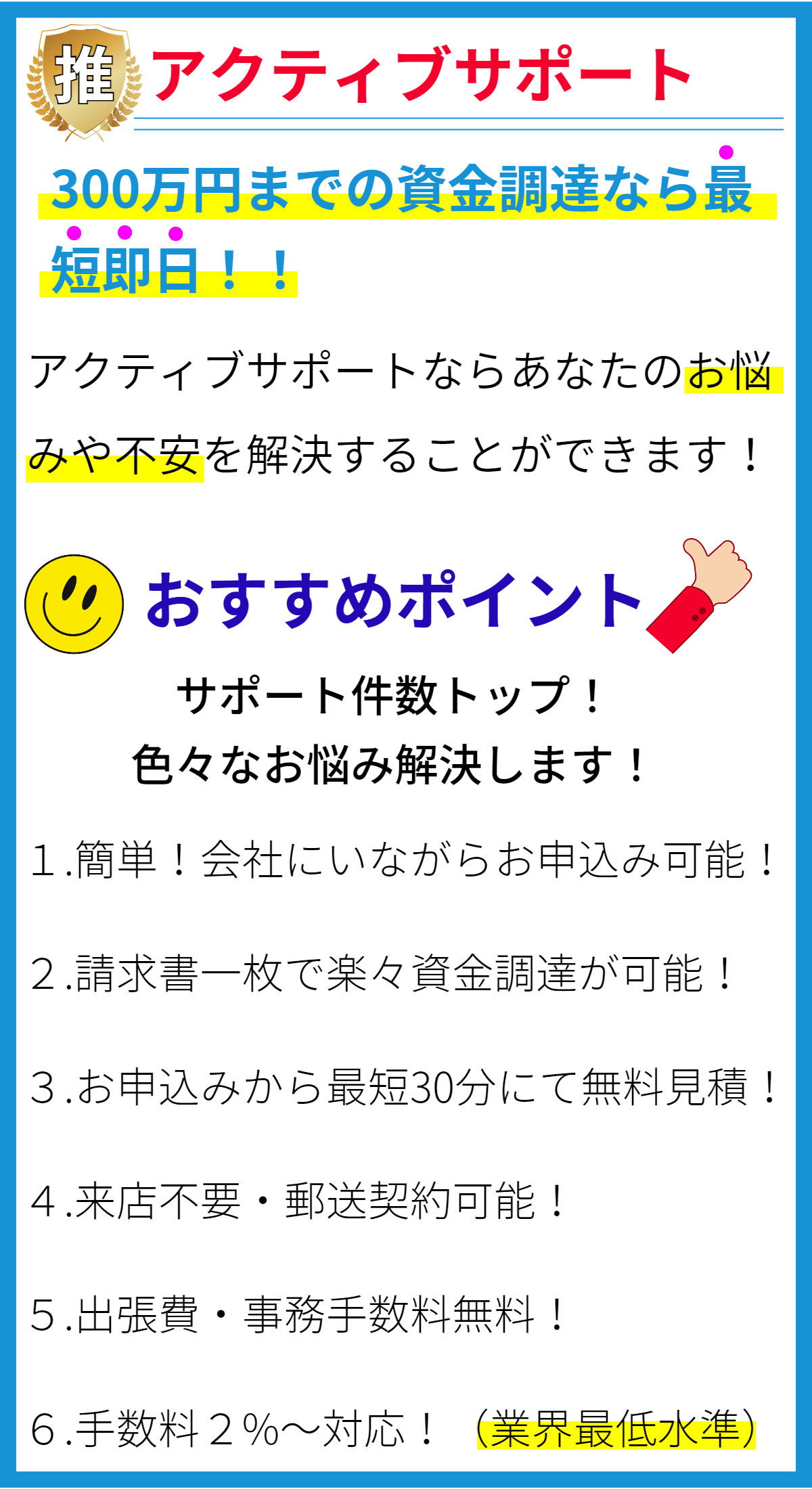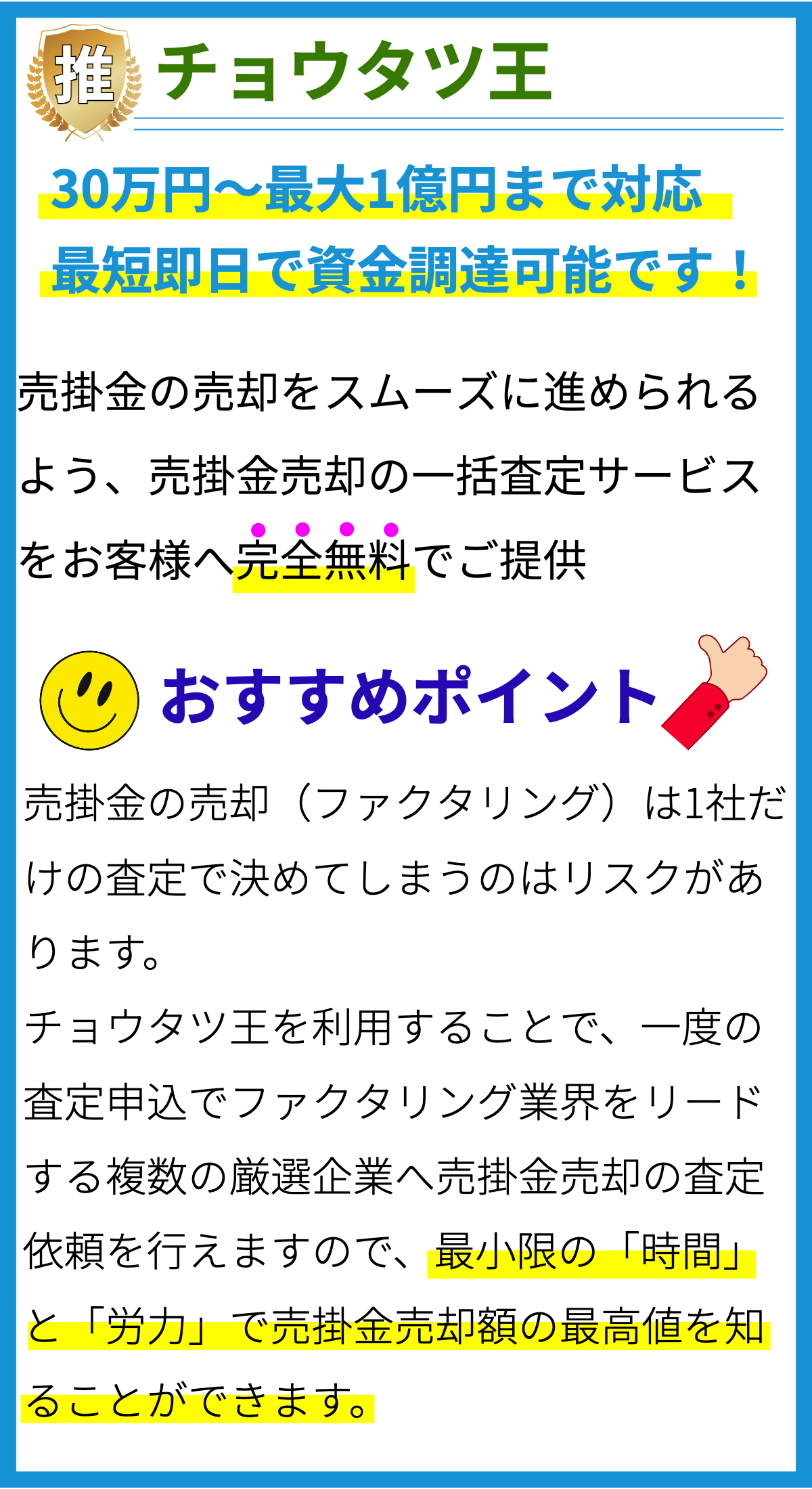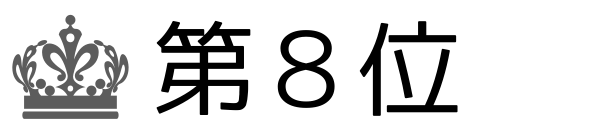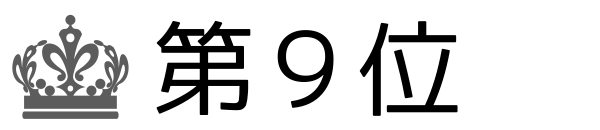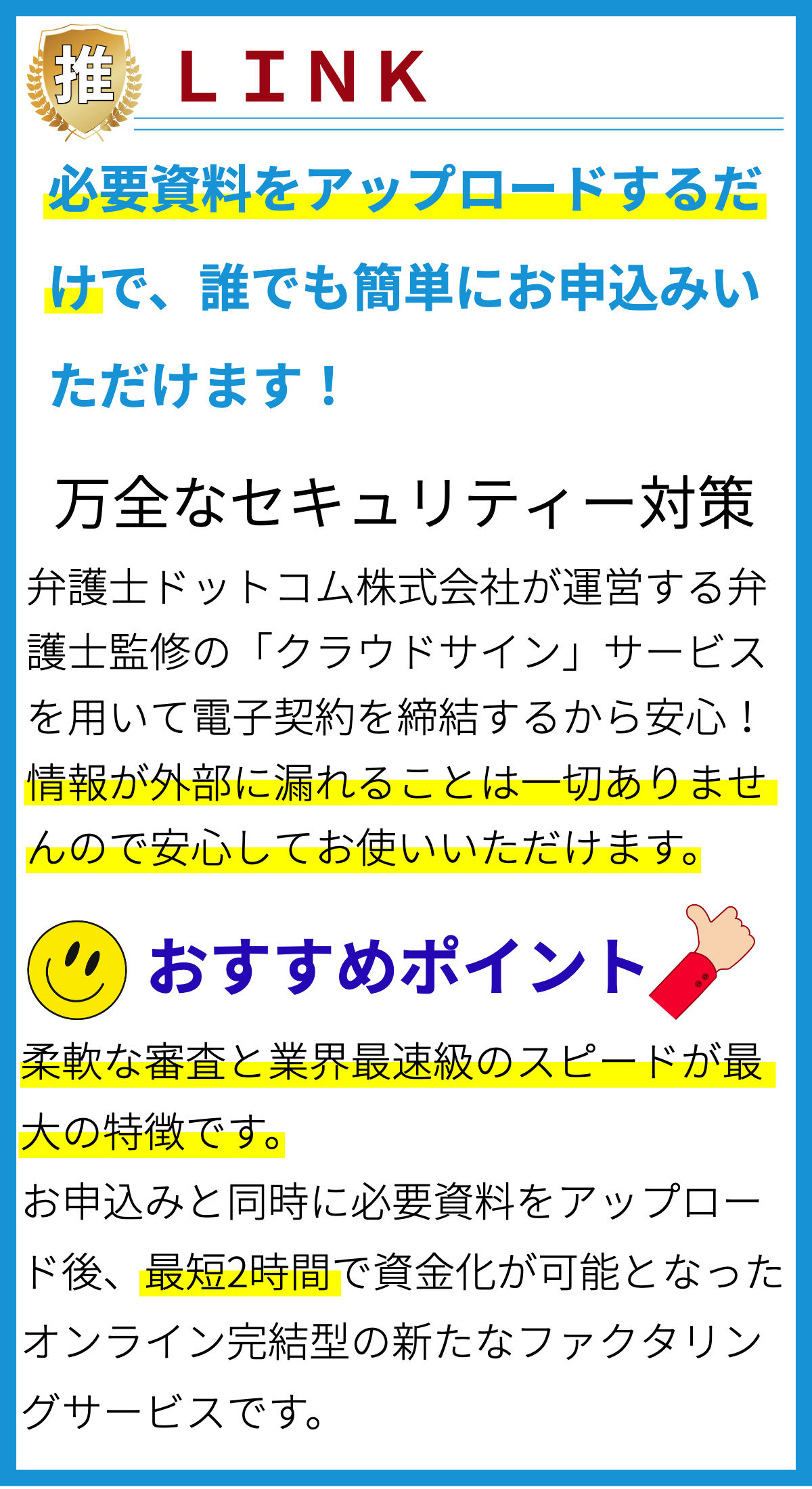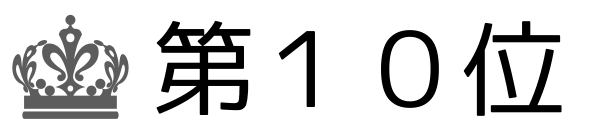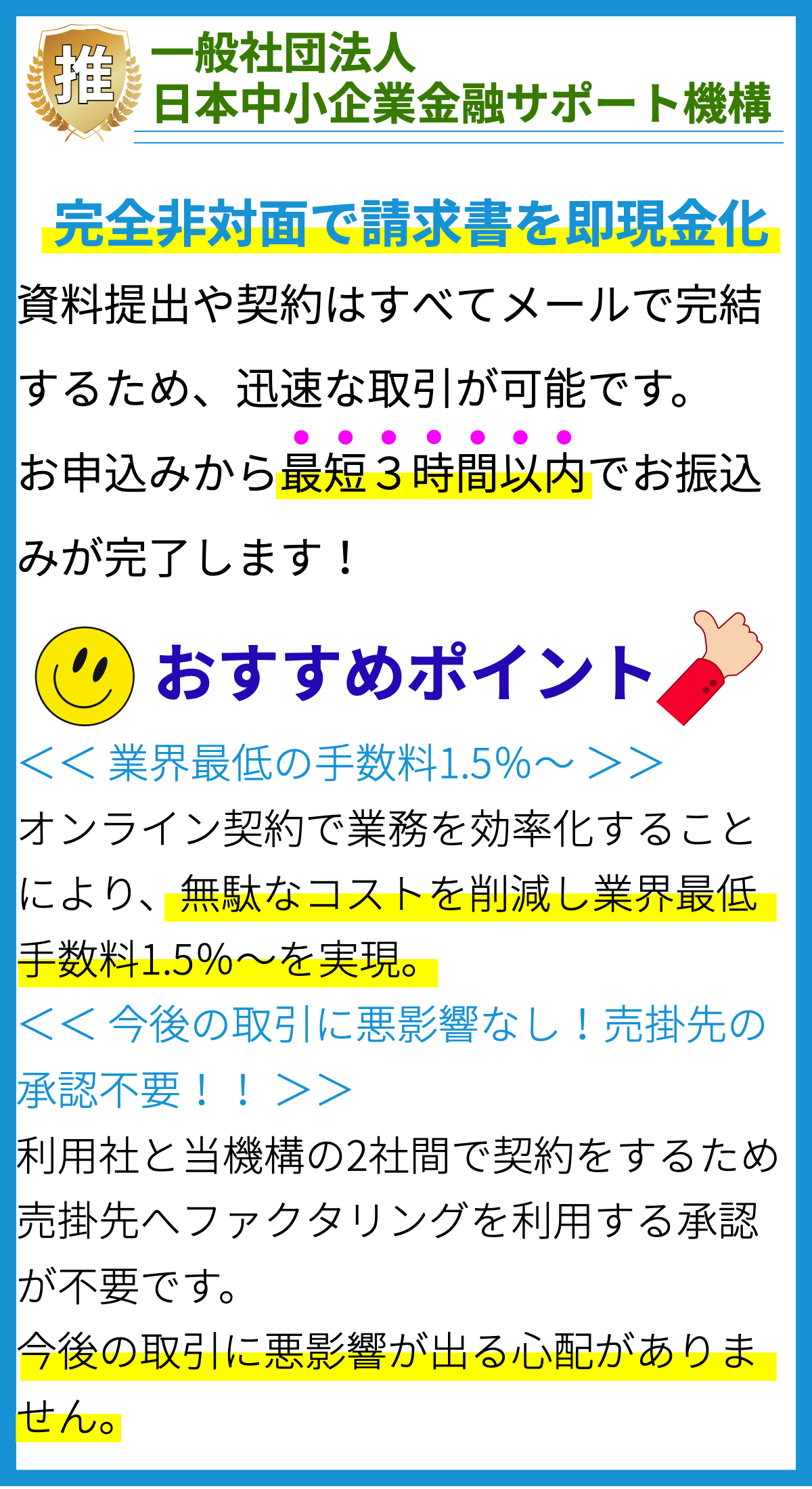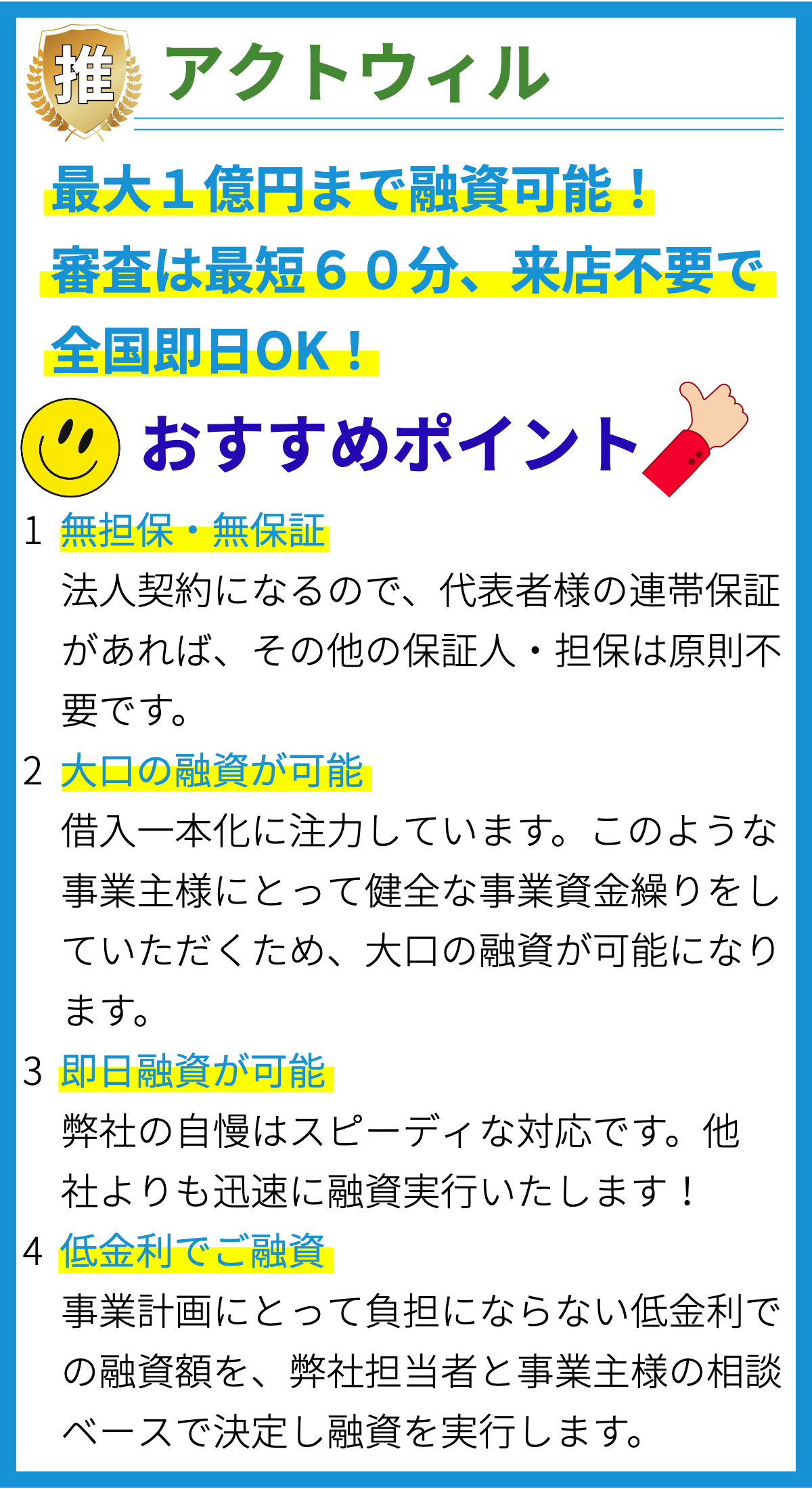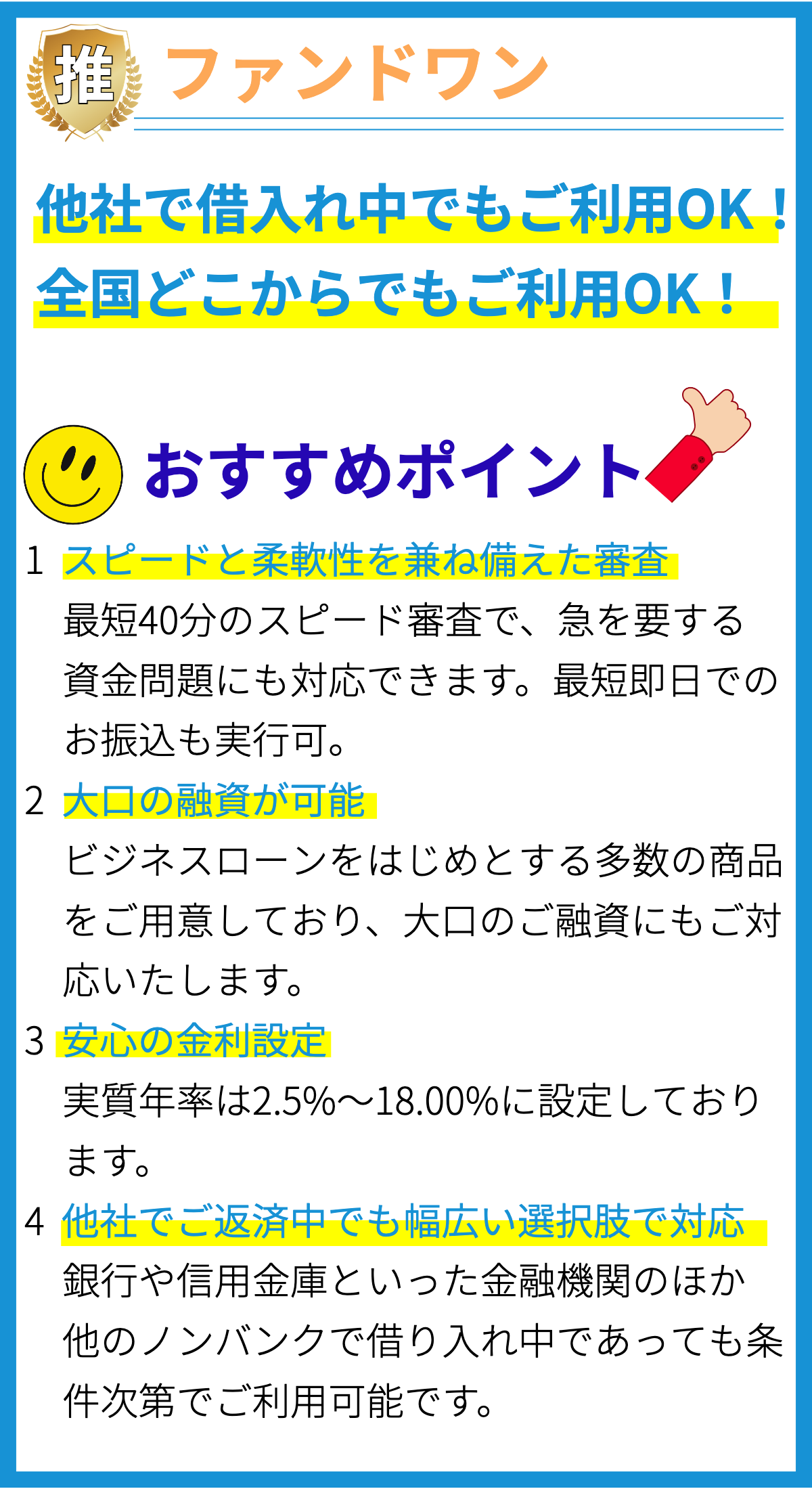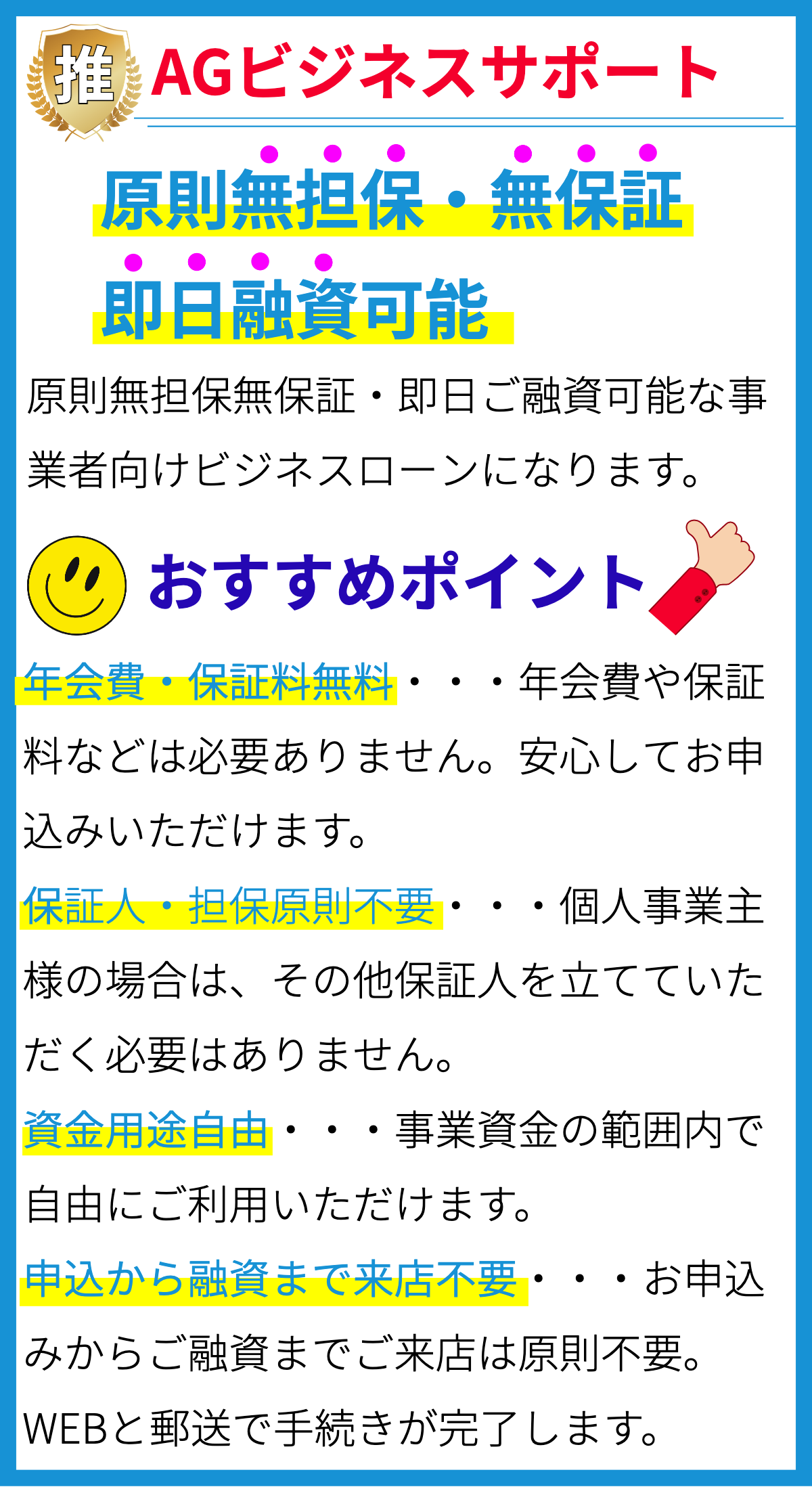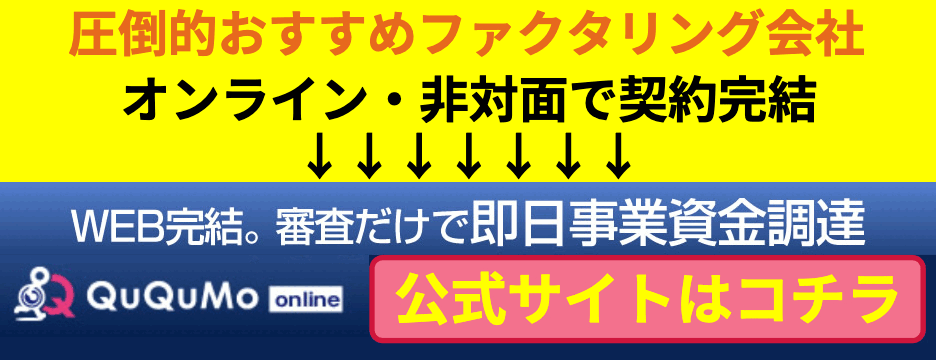【PR】
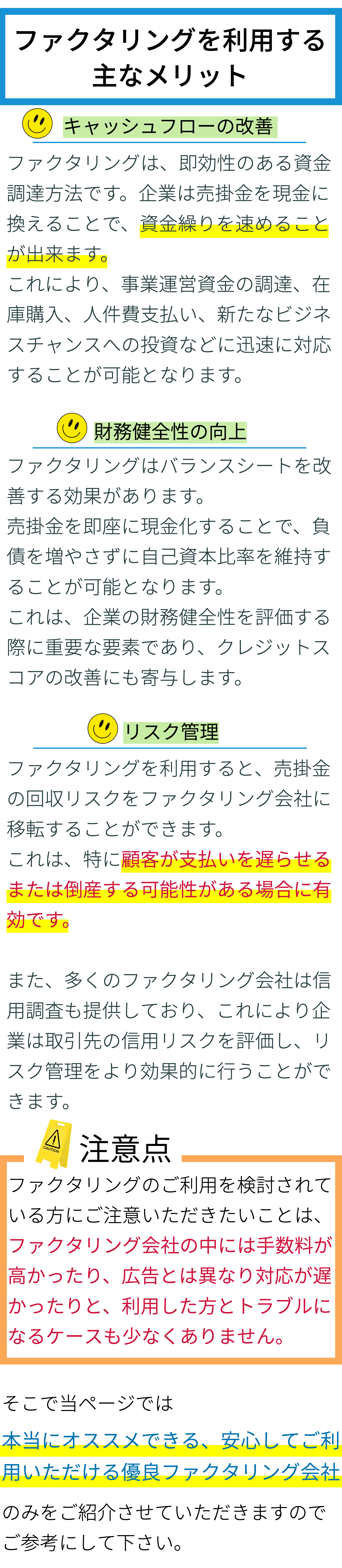

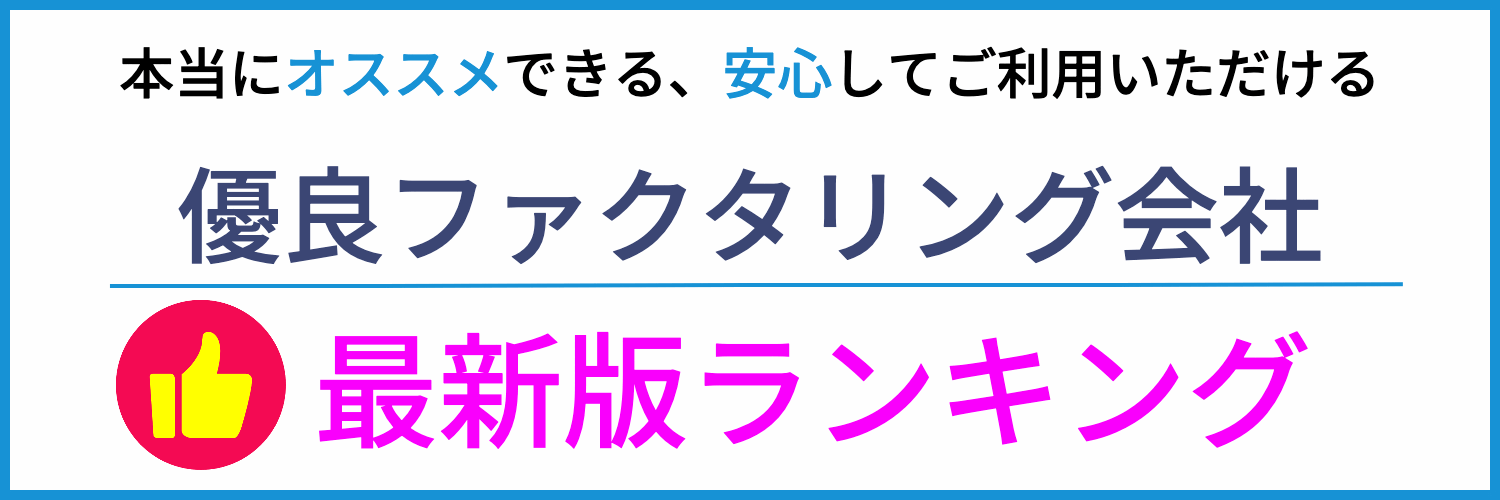
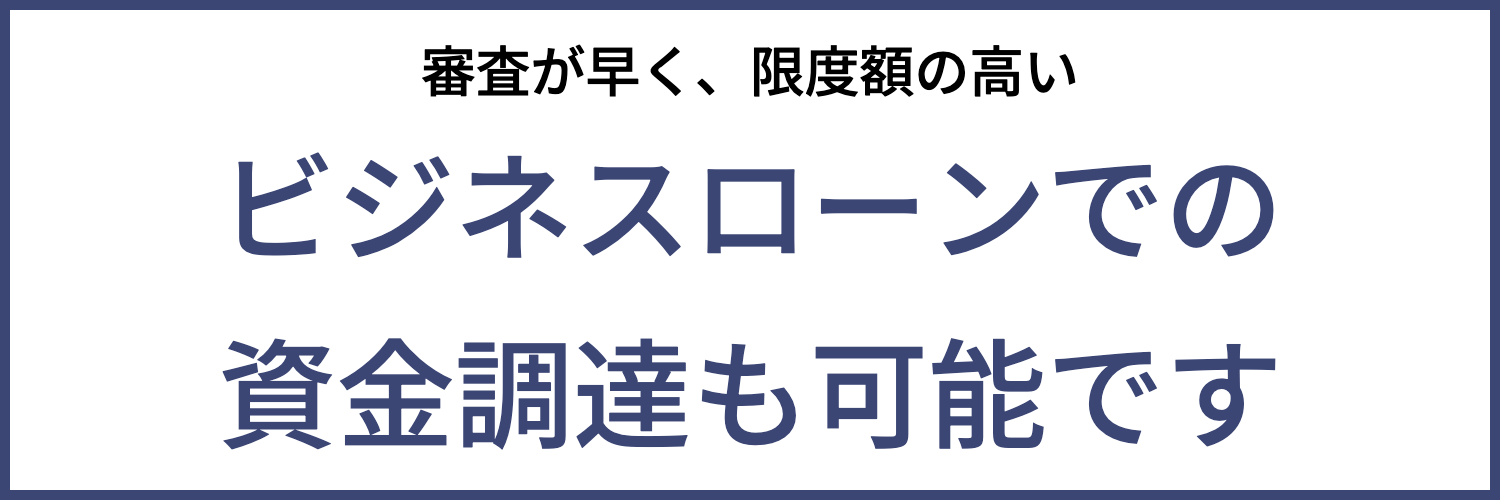
ファクタリングについて
ファクタリングは、企業が未収金の請求書を金融機関や専門の会社に売却し、現金を受け取る手法です。以下はファクタリングについての詳細です。
資金調達の必要性
企業が成長し、運営資金を確保する必要がある場合、資金調達が必要になります。資金調達の方法として、ファクタリングが一つの選択肢となります。
ファクタリングの仕組み
ファクタリングは以下の手順で行われます。
- 企業は未収金の請求書を選定し、ファクタリング会社に提出します。
- ファクタリング会社は請求書の信用調査を行い、請求書の妥当性を確認します。
- ファクタリング会社は請求書に対する前払金(通常は一定割合)を企業に支払います。
- ファクタリング会社は請求書の回収を担当し、収益を上げるために最善の方法を検討します。
- 請求書の額面から手数料や利息を差し引いた残額が、企業に支払われます。
ファクタリングの利点
ファクタリングは以下の利点を持っています。
- 即座の現金調達: 未収金を現金化するため、資金を素早く確保できます。
- 信用リスクの軽減: ファクタリング会社が信用調査と回収を行うため、債権に関するリスクが軽減されます。
- 運用キャッシュの最適化: 企業は未収金を活用し、運用キャッシュを最適化することができます。
ファクタリングのデメリット
一方で、ファクタリングには以下のデメリットも存在します。
- 費用の負担: ファクタリング手数料や利息などが発生し、コストがかかることがあります。
- 顧客関係の損失: 未収金の回収がファクタリング会社に委託されるため、顧客との信頼関係に悪影響を及ぼすことがある。
- 長期的なコスト: 短期的な資金調達手段として便利ですが、長期的なコストが高くつくことがある。
ファクタリングと似た手法
資金調達を検討する際、ファクタリング以外の手法も考慮する価値があります。代表的なものには次のようなものがあります。
- 銀行融資: 銀行からの融資を受けることで、資金を調達できます。しかし、信用評価や返済条件が影響を及ぼすことがある。
- 株式発行: 株式を発行し、株主から資金を調達する方法です。株主への配当や経営権の一部譲渡が発生します。
- 債券発行: 債券を発行し、債券保有者から資金を調達します。定期的な利息支払いが必要です。
ファクタリングの適用例
ファクタリングは特定の業種や状況に適しています。以下はその適用例です。
- 小規模企業: 資金調達のオプションが限られている小規模企業にとって、ファクタリングは魅力的な選択肢となります。
- 季節性ビジネス: 季節によって売上が大きく変動するビジネスは、ファクタリングを通じてキャッシュフローを安定化させることができます。
- 新興企業: 成績が不安定な新興企業は、伝統的な融資手法が難しい場合があり、ファクタリングが有用です。
まとめ
ファクタリングは資金調達の手法の一つで、未収金を現金化する方法です。利点とデメリットを検討し、企業の特定の状況に適しているかどうかを判断することが重要です。また、他の資金調達手法と比較検討し、最適な選択肢を見つけることも大切です。